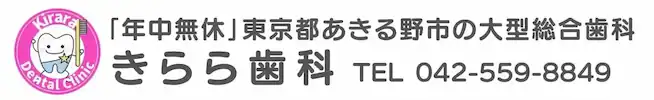親知らずが痛む原因とは?
親知らず(智歯・第三大臼歯)が痛む主な原因は以下の通りです。
① 親知らずの周囲の炎症(智歯周囲炎)
親知らずの周囲に汚れや細菌が溜まると、歯茎に炎症が起きて痛みます。特に親知らずは一番奥にあるため磨きづらく、不衛生になりがちで炎症(智歯周囲炎)が起こりやすいです。
智歯周囲炎の主な症状
- 歯茎の腫れ、出血、痛み
- 口が開けにくくなる
- 頬が腫れる
- 口臭が強くなる
- 発熱する場合もある
智歯周囲炎を放置するとどうなるか?
- 炎症が周囲の骨まで広がり、顔が腫れることがあります。
- 顎の下や首周りまで感染が広がるリスクがあります(蜂窩織炎)。
親知らずが痛む主な原因(詳しく解説)
親知らずの痛みを引き起こす原因は以下のようなものが多いです。
1. 親知らずの虫歯(齲蝕)
親知らずは歯ブラシが届きにくいため、虫歯になりやすい歯です。進行すると激しい痛みを伴います。
2. 隣の歯に影響を与える(第二大臼歯の虫歯・歯周病)
親知らずが横向きや斜めに生えていると、隣の歯にぶつかり、虫歯や歯周病の原因になります。
3. 埋伏した親知らずによる痛み
親知らずが正常に生えず、斜めや横向き、あるいは骨の中で埋伏したままのケースがあります。周囲の骨や神経を圧迫して、痛みや腫れの原因になります。
4. 咬合性外傷(噛み合わせによる痛み)
上下の親知らずの噛み合わせが悪い場合、歯や歯茎に無理な力がかかり、慢性的な痛みが生じることもあります。
親知らずの痛みの治療法
痛みがある場合、次のような治療を行います。
①薬物療法(痛み止め・抗生剤)
- 急な痛みや腫れが強い場合、抗生物質と鎮痛剤で症状を抑えます。
②消毒・クリーニング
- 歯茎の炎症を軽減するため、歯垢や歯石の除去・消毒を行います。痛みが一時的に改善することがあります。
②抜歯(親知らずを抜く治療)
- 親知らずが繰り返し炎症を起こす場合や、隣の歯に悪影響を与えている場合は抜歯が推奨されます。
- 特に埋伏歯(歯が骨に埋まっている)では手術が必要なこともあります。
親知らずを抜くべきかどうかの判断基準
痛みがある親知らずについて「抜くべきか・抜かなくてもよいか」の判断基準を整理します。
抜歯が推奨されるケース
以下の場合は親知らずを抜くメリットが大きいです。
- 何度も痛みや腫れを繰り返す場合
- 隣の歯(第二大臼歯)が虫歯や歯周病になってしまった場合
- 親知らず自体が重度の虫歯になった場合
- 埋伏している親知らずが他の歯を圧迫したり、歯並びを悪化させている場合
- 親知らず周囲に嚢胞(のうほう)がある場合
抜かなくてもよいケース
次のような場合は、無理に抜く必要がないこともあります。
- まっすぐ正常に生えており、ブラッシングも十分できている場合
- 痛みや腫れ、虫歯などのトラブルが起きていない場合
- 将来的に他の歯のブリッジや義歯を支える土台として使える可能性がある場合
親知らずの抜歯は痛いのか?
抜歯の際には必ず局所麻酔を使用するため、抜歯の手術中は痛みを感じることはありません。ただし、抜歯後の数日間は痛みや腫れが生じることがあります。
抜歯後の痛みの対処法
- 抜歯後は痛み止めの薬を処方します。
- 痛みや腫れは通常数日〜1週間程度で改善します。
- 氷で冷やす、安静にするなどのケアで痛みを軽減できます。
親知らずを抜歯後の注意点とケア方法
親知らずを抜いた後の注意点を説明します。
- 抜歯した日は激しい運動や飲酒、喫煙を控える
- 抜歯当日は強いうがいを避ける
- 抜歯後24時間は強い運動、入浴、飲酒は避ける
- 傷口を舌で触ったり、強くすすいだりしない
- 出された薬をきちんと飲む
- 食事は柔らかく刺激の少ないものを選ぶ
親知らずの痛みを防ぐための日常ケアのポイント
- 親知らず周囲を重点的に清掃し、歯ブラシだけでなくフロスや歯間ブラシを活用する
- 定期的な歯科検診で親知らずの状態を確認する
- 痛みが出る前に抜歯することでトラブルを防ぐことができる
まとめ
親知らずが痛む場合、放置すると深刻な問題につながります。
原因に応じて適切な処置を早めに受けることが重要であり、抜歯が必要な場合は早めに行うことで周囲の歯や口腔環境の健康維持につながります。
まずは歯科医院を受診し、担当医と相談しながら「抜くべきかどうか」を判断することをおすすめします。