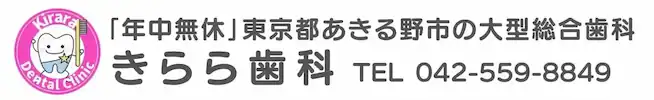歯牙腫(しがしゅ)とは
歯牙腫とは、歯をつくる細胞が異常に増殖してできる良性の歯原性腫瘍です。
「腫瘍」という言葉がつきますが、多くの場合はがんのように悪性ではなく、骨の中で歯の成分(エナメル質・象牙質・歯髄など)が不規則に形成された塊として発見されます。
成長はゆるやかで、痛みもほとんどないため、歯科検診やX線撮影で偶然見つかることが多い病変です。
歯牙腫は歯原性腫瘍(しげんせいしゅよう)に分類され、その中でも「発育性異常」に近い性質を持つため、腫瘍と奇形の中間的な存在とされています。
歯の組織を構成する細胞(エナメル芽細胞・象牙芽細胞など)が歯列の外で異常に増殖し、歯のような構造を作ってしまうのが特徴です。
歯原性腫瘍(しげんせいしゅよう)とは、歯をつくる細胞(エナメル上皮・歯乳頭・歯嚢など)から発生する腫瘍の総称です。多くは良性ですが、一部には再発や悪性化の可能性をもつものもあります。代表的なものとして、エナメル上皮腫(顎骨内でゆっくり膨張する腫瘍)、歯牙腫(歯の成分が異常に増殖した塊)、セメント質腫、歯原性角化嚢胞、歯原性線維腫などがあります。これらは顎骨内に発生し、X線で不透過像や透過像として確認されることが多く、無症状で進行するケースも少なくありません。治療は多くが外科的摘出で、良性のものは完全除去により再発を防ぐことができます。
歯牙腫の分類
歯牙腫は主に次の2つのタイプに分けられます。
① 集合性歯牙腫(しゅうごうせいしがしゅ)
複数の小さな歯のような構造(歯牙様構造)が密集してできるタイプです。
通常、上顎の前歯部に多く見られ、レントゲンで「小さな歯がたくさん並んでいるような像」を呈します。
形成された小歯が20〜30個近く確認されることもあり、まるでミニチュアの歯が集まっているように見えることもあります。
このタイプは比較的若年者に多く、永久歯の萌出を妨げる原因として発見されることが多いのが特徴です。
② 複雑性歯牙腫(ふくざつせいしがしゅ)
歯の硬組織(エナメル質・象牙質・セメント質など)が、正常な歯の形をとらずに不規則に塊状に形成されたタイプです。
見た目は白色〜淡黄色の硬い塊で、レントゲンでは不透過性の不整形な陰影として映ります。
下顎の奥歯(大臼歯部)に多く見られ、集合性歯牙腫に比べてやや大きくなる傾向があります。
どちらのタイプも良性で、転移や浸潤性の進行はありませんが、成長に伴って顎骨を膨らませたり、隣の歯の萌出を妨げたりすることがあります。
発生の原因
歯牙腫の正確な原因はまだ明確には解明されていませんが、以下のような要因が関係すると考えられています。
- 歯の形成期におけるエナメル上皮や歯乳頭の発育異常
- 遺伝的要素(家族内での発生報告もあります)
- 外傷や感染などによる歯胚(歯の芽)の損傷
- 埋伏歯や過剰歯の形成異常との関連
特に、乳歯から永久歯へ生え変わる時期に起こることが多く、歯の発育に関わる細胞が過剰に反応してしまうことで発生すると考えられています。
好発部位と発症年齢
歯牙腫は子どもから若年成人までの10〜30歳代に多く見られます。
部位としては、
- 集合性歯牙腫 → 上顎前歯部(中切歯・側切歯の周辺)
- 複雑性歯牙腫 → 下顎臼歯部(特に親知らず周辺)
に好発します。
男女差はほとんどありませんが、集合性タイプは女性にやや多い傾向があります。
主な症状
歯牙腫は多くのケースで無症状です。
そのため、定期検診や矯正治療前のX線検査で偶然見つかることがほとんどです。
しかし、以下のような症状が現れることもあります。
- 永久歯がなかなか生えてこない
- 顎の一部が膨らんでいる
- 歯列の一部にしこりや硬い感触がある
- 乳歯が抜けたのに後続歯が萌出しない
成長して大きくなると、骨を圧迫して顎の変形を起こしたり、隣の歯根を吸収したりすることもあります。
感染を伴うと、痛みや腫れが出る場合もあります。
診断方法
① レントゲン検査
歯牙腫は、レントゲンで歯に似た硬組織が密集している像として映ります。
集合性タイプでは多数の小さな歯が並ぶ像、複雑性タイプでは塊状の不透過像を示します。
② CT検査
CT撮影により、腫瘍の正確な位置や大きさ、周囲の神経・歯根との関係を立体的に把握できます。
これにより、安全な手術計画を立てることができます。
③ 病理組織検査
摘出した歯牙腫を顕微鏡で観察し、歯の構造を持つかどうかを確認します。
エナメル質・象牙質・セメント質などの構造が確認できれば確定診断となります。
治療方法
1. 外科的摘出
治療の基本は、外科的に歯牙腫を摘出することです。
局所麻酔での手術が一般的で、腫瘍の位置が深い場合や大きい場合は、静脈内鎮静や全身麻酔下で行うこともあります。きらら歯科では徳洲会病院や大学病院にご紹介させていただいております。
手術の流れ:
- 歯ぐきを切開して骨を一部開削
- 歯牙腫を慎重に除去
- 近接する永久歯や神経を保護
- 縫合
2. 萌出誘導
歯牙腫が永久歯の萌出を妨げていた場合、摘出後にその歯が自然に生えてくることもあります。
萌出しない場合は、矯正装置を使って牽引する方法をとることもあります。
3. 再発防止
歯牙腫は良性のため、完全に除去できれば再発はほとんどありません。
ただし、残存組織が残った場合には再発する可能性があるため、CTによる術後確認が重要です。
術後の経過と注意点
術後は一時的に腫れや痛みが出ることがありますが、数日で落ち着くことがほとんどです。
骨の欠損部は数ヶ月かけて自然に再生していきます。
摘出後のスペースに新しい歯が萌出するかどうかは、歯胚の状態によって異なります。
感染予防のための抗生剤投与や、軟食・うがいなどの指導を受け、清潔を保つことが大切です。
放置した場合のリスク
歯牙腫は痛みがないため、放置されることがあります。
しかし、そのままにしておくと以下のような問題が起こる可能性があります。
- 永久歯の萌出障害
- 顎の膨隆や顔の非対称
- 隣接歯の根吸収
- 咬み合わせのずれ
- 囊胞化や感染
特に成長期の子どもでは、顎骨の変形や歯列不正につながることもあるため、早期発見・早期摘出が重要です。
他の疾患との違い
歯牙腫と似た所見を示す疾患には、以下のようなものがあります。
- 含歯性嚢胞
- 歯原性角化嚢胞
- エナメル上皮腫
- 過剰歯
これらはいずれも歯の形成組織から発生する病変ですが、歯牙腫は歯の形を持つ硬組織が形成されている点が最大の特徴です。
CTや病理診断によって鑑別が行われます。
予後
歯牙腫は摘出により完全治癒が期待できる良性病変です。
再発率は極めて低く、術後も正常な顎骨構造が再生します。
ただし、埋伏していた歯の萌出や歯列への影響を確認するため、術後半年〜1年は定期的な経過観察が推奨されます。
きらら歯科では、CTによる三次元診断と経験豊富な口腔外科医による精密な手術を行い、機能的・審美的な回復を目指しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 歯牙腫はがんですか?
→ いいえ。歯牙腫は良性の腫瘍で、転移や悪性化の心配はほとんどありません。
Q. 痛みがないのに手術が必要ですか?
→ はい。放置すると顎の骨が変形したり、歯の萌出が妨げられるため、早期摘出が望まれます。
Q. 手術後にまたできることはありますか?
→ ほとんどありません。再発はまれですが、定期的なレントゲンで確認します。
Q. 子どもでも手術できますか?
→ 可能です。成長期に発見された場合は、永久歯の萌出を考慮したタイミングで安全に摘出します。
まとめ
歯牙腫は、歯の成分が異常に増殖してできる良性の歯原性腫瘍です。
ほとんどは痛みがなく、X線検査で偶然発見されますが、放置すると永久歯の萌出を妨げたり、顎骨を膨らませたりすることがあります。
外科的に除去すれば再発の心配はほとんどなく、早期発見・適切な処置で良好な経過が得られます。