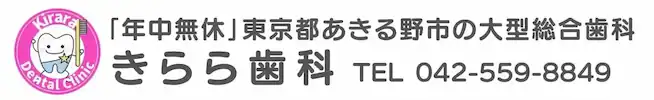含歯性嚢胞(がんしせいのうほう)とは
含歯性嚢胞とは、まだ歯ぐきの中や顎の骨の中に埋まっている歯(埋伏歯) のまわりに、袋状の病変ができる疾患です。
この袋の中には液体がたまり、次第に大きくなることで、顎の骨を押し広げたり、隣の歯を圧迫したりすることがあります。
「含歯」という言葉は「歯を含む」という意味で、嚢胞(のうほう)は「袋状の空間」を指します。つまり、歯を包み込むようにできる袋状の病変ということです。
発生の原因
歯が骨の中で形成される過程で、歯冠のまわりには「エナメル上皮」と呼ばれる薄い膜状の組織が存在します。
通常、この上皮は歯が萌出(ほうしゅつ)するとともに吸収されていきますが、萌出せずに埋伏したままになると、この上皮が袋状に膨らみ、液体が溜まって嚢胞化してしまうことがあります。
このようにしてできる含歯性嚢胞は、歯の発生に関連した「発育性の歯原性嚢胞」 に分類されます。
親知らず(智歯)や犬歯、小臼歯など、萌出しにくい歯のまわりに発生しやすい傾向があります。
エナメル上皮とは、歯ができる過程で歯胚(しはい)と呼ばれる歯の芽を構成する細胞の一部で、後に歯の表面を覆うエナメル質をつくるもととなる組織です。歯の発生初期に外胚葉から分化し、歯冠の形成に関与します。通常は歯の萌出後に消失しますが、埋伏歯のまわりに残ると、含歯性嚢胞などの歯原性病変の原因になることがあります。
好発部位と年齢層
最も多いのは下顎の親知らずのまわりにできるケースです。
次いで、上顎の犬歯や過剰歯(余分に生えてこない歯)に関連して発生する場合もあります。
年齢的には10代後半〜30代が中心で、永久歯が完成して間もない時期から若年成人に多く見られます。
しかし、中高年になってから偶然レントゲンで発見されることも少なくありません。
症状と経過
含歯性嚢胞は初期段階ではほとんど症状がありません。
痛みも腫れもなく、歯科検診や親知らずのレントゲン撮影で偶然見つかることが多いのが特徴です。
嚢胞が大きくなってくると、
特に感染を起こすと、顎や頬が腫れ、口が開きにくくなったり、発熱を伴ったりすることもあります。
また、骨が薄くなりすぎると、強い力がかからなくても骨折してしまうこともあります。
含歯性嚢胞は、埋伏歯の歯冠を包むように形成される袋状の病変で、長期間放置すると徐々に拡大し、周囲の骨を吸収・菲薄化させます。嚢胞が大きくなると顎骨の内部が空洞化し、外側の骨が薄くなるため、わずかな衝撃でも骨折が起こる危険性があります。特に下顎智歯部では、嚢胞が下顎管や下縁に近い位置に達すると、下顎骨の強度が著しく低下します。骨折を防ぐためには、早期に嚢胞を摘出し、骨の再生を促すことが重要です。放置は顔貌変形や神経麻痺を伴う骨折につながる恐れがあります。
診断方法
診断には、レントゲン検査やCT撮影 が有効です。
含歯性嚢胞は、埋伏歯の歯冠を中心に、境界が明瞭な丸い黒い影(透過像)として映ります。
CTを用いると、嚢胞の大きさ・位置・隣の歯や神経との関係を三次元的に確認でき、安全な手術計画を立てることができます。
診断時には、似たような病変(歯原性角化嚢胞、エナメル上皮腫など)との鑑別が必要です。
確定診断のためには、摘出した嚢胞壁の組織を病理検査で調べることがあります。
治療方法
基本方針
治療は外科的に嚢胞を取り除くこと(摘出)が基本です。嚢胞を作っている埋伏歯が原因であるため、埋伏歯の抜歯を同時に行うことが多いです。
嚢胞が小さい場合は、局所麻酔で日帰りの手術が可能です。一方、嚢胞が大きい場合や神経・副鼻腔に近い場合は、入院・全身麻酔下での処置が必要になることもあります。
処置の流れ
- 局所または静脈内鎮静で麻酔
- 歯ぐきを切開して骨を開け、嚢胞と歯を摘出
- 必要に応じて、嚢胞腔を清掃・骨補填
- 縫合し、約1〜2週間後に抜糸
手術後は抗生剤と痛み止めを処方し、定期的に経過観察を行います。骨が自然に再生してくるまで、数ヶ月〜半年ほどかかる場合もあります。
手術後の注意点
術後は、数日間腫れや痛みが出ることがありますが、通常は徐々に落ち着いていきます。
血流を良くしすぎる行為(長風呂・激しい運動・飲酒など)は控える必要があります。
また、抜糸までは清潔保持を意識し、刺激物を避けたやわらかい食事が望ましいです。
まれに、下顎の神経に近い部位では、唇や顎のしびれを一時的に感じることがあります。
ほとんどは時間とともに回復しますが、術前にCTで神経走行を確認し、リスクを最小限にすることが重要です。
放置した場合のリスク
含歯性嚢胞を放置すると、時間をかけてゆっくりと大きくなります。
進行すると以下のような問題が起こる可能性があります。
- 顎骨の変形・骨の菲薄化
- 隣接歯の根吸収や動揺
- 咬み合わせのズレ
- 膿瘍形成や骨髄炎
- 稀に腫瘍性変化(まれにエナメル上皮腫などに変化することも)
このように、痛みがなくても放置は危険です。
レントゲン検査で埋伏歯が見つかった場合は、嚢胞の有無を確認しておくことが大切です。
予防と早期発見のポイント
含歯性嚢胞は「無症状で進行する」ことが最も注意すべき点です。
そのため、定期的な歯科検診とレントゲン撮影が最大の予防策になります。
特に以下のような方は注意が必要です。
- 親知らずが生えてこない、もしくは横向きになっている
- 過剰歯(余分な歯)があるといわれた
- 永久歯がなかなか生えてこないお子様
また、歯科医院でのパノラマX線検査やCT検査を定期的に行うことで、早期発見・早期治療が可能になります。
再発について
含歯性嚢胞は、摘出が不完全な場合や感染を繰り返す場合に再発することがあります。
再発防止のためには、嚢胞壁を完全に除去すること、そして術後も定期的に画像検査で経過を追うことが大切です。
きらら歯科では、術後3〜6ヶ月ごとのレントゲンフォローを行い、再発がないかを確認しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 痛みがないのに治療が必要ですか?
→ はい。無症状でも、嚢胞はゆっくりと拡大し、骨を溶かしてしまうことがあります。早期治療が最も安全です。
Q. 手術は入院が必要ですか?
→ 多くの場合、局所麻酔または静脈内鎮静で日帰り手術が可能です。大きな嚢胞や神経近接例では入院が必要な場合もあります。
Q. 放置するとどうなりますか?
→ 顎の骨が変形したり、隣の歯を失うことがあります。まれに膿がたまり、顔が腫れることもあります。
Q. 手術後は歯を残せますか?
→ 病変の位置や大きさによりますが、早期発見であれば埋伏歯を保存できることもあります。
まとめ
含歯性嚢胞は、親知らずや埋伏歯のまわりにできる代表的な顎骨内病変です。初期には痛みがないため、気づかぬうちに大きくなることがありますが、早期発見・適切な外科処置によって完治が可能です。きらら歯科では含歯性囊胞を発見した場合にはご説明させていただき高度医療機関にご紹介させていただいております。