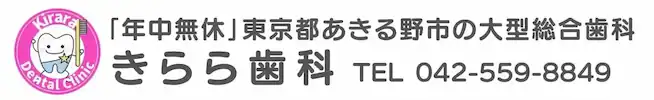抜歯をお考えの方へ|あきる野・福生・青梅・八王子エリアの歯科医院
虫歯や歯周病が進行し、歯の治療では改善が難しい場合、抜歯が必要になることがあります。
歯の痛みやトラブルでお悩みの方へ、きらら歯科では患者様の痛みなどの負担を極力抑えた抜歯治療を提供しています。親知らずの抜歯から、虫歯や歯周病による抜歯まで、専門的な技術と最新の設備を活用し、安心・安全な治療を心がけています。

親知らずを抜いたほうがいいのか判断がつかない方も、お気軽にご相談ください。歯科医師が相談をお受けし、患者さまの状態をよく分析したうえで抜歯をすべきか、どのような治療方法が考えられるか、といった点について丁寧にお答えします。
抜歯の主な理由
- 重度の虫歯:虫歯が進行し、根管治療では対応が難しい場合、抜歯が必要です。
- 重度の歯周病:歯を支える骨が減り、歯が動揺する場合に抜歯が検討されます。
- 矯正治療:歯並びを改善するために、スペースを作る目的で抜歯することがあります。
- 親知らずの問題:親知らずが正しく生えていない場合や、他の歯に悪影響を与える場合、抜歯が推奨されることがあります。
抜歯の流れ
診査・診断
まず、レントゲン撮影や視診・触診を行い、抜歯の必要性や難易度を確認します。レントゲンで診断できない場合には、必要に応じてCT撮影を行うこともあります。

また高血圧などの持病や服用薬がある場合は、全身状態を考慮した診療計画を立てます。
麻酔の実施
表面麻酔を使用したのち局所麻酔を行い、痛みを最小限に抑えます。
表面麻酔は、歯科治療時の針の刺入時の痛みを軽減するために使用されます。粘膜に塗布することで神経の感覚を鈍らせ、注射時の不快感を和らげる効果があります。

抜歯の実施
歯を揺らしながら慎重に抜歯します。埋まっている歯や根が複雑な歯の場合は、歯を分割するなど適切な方法で取り除きます。
抜歯に使用する器具には、歯を的確に把持し、安全に抜去するためのさまざまな器具があります。主に使用されるのは、エレベーター(挺子)と抜歯鉗子です。エレベーターは歯と歯槽骨の間に挿入し、歯を動かして抜きやすくする器具です。一方、抜歯鉗子は歯をしっかりと把持し、適切な方向に動かしながら抜去します。さらに、難抜歯の場合は、バーや骨ノミ、ペリオトームを用いて骨を削ったり、歯根を分割することもあります。
一般的な抜歯(単純抜歯)
比較的簡単な抜歯で、動揺している歯や歯根が単純な構造の歯に適用されます。
① 歯の動揺
専用のエレベーター(ヘーベル)を使い、歯をゆっくりと揺らして骨との隙間を広げます。
② てこの原理で持ち上げる
エレベーターを歯根と骨の間に挿入し、てこの原理を利用して歯を浮かせます。
③ 鉗子(抜歯鉗子)で抜く
鉗子を歯にしっかりと装着し、左右に回転・揺らしながらゆっくりと引き抜きます。
止血・縫合
抜歯後はガーゼを噛んで圧迫止血します。縫合が必要な場合は、後日抜糸が必要な糸で縫合します。
術後の説明と投薬
術後の注意事項(うがいの控え方、食事制限、安静の重要性など)を説明し、必要に応じて抗生剤や鎮痛剤を処方します。
経過観察と抜糸(必要時)
1週間後を目安に経過を確認し、縫合した場合は抜糸を行います。その後、傷口の治癒状況を見ながら必要なケアを続けます。抜歯後の適切なケアを行うことで、感染やドライソケット(血餅が取れてしまう状態)を防ぎ、スムーズな回復を促します。
ドライソケットとは、抜歯後に血餅(かさぶた)が適切に形成されず、歯槽骨が露出してしまう状態です。通常、血餅が傷口を保護し治癒を促しますが、喫煙やうがいのしすぎなどで剥がれると、強い痛みや炎症が生じます。特に下顎の親知らず抜歯後に起こりやすいです。治療には洗浄や鎮痛剤の使用が必要で、予防には抜歯後の適切なケアが重要です。
抜歯後の注意事項

抜歯の後、しっかりとケアをすることで回復を早め、次の治療にスムーズに移行できるようになります。
抜歯後の痛みの対処法
痛みのピークと期間
痛みは抜歯後の麻酔が切れる数時間後から始まり、2~3日目にピークを迎えることが多いです。その後、徐々に落ち着き、1週間程度でほとんど気にならなくなります。
痛み止めの使用
- 痛みが強くなる前に、歯科医院で処方された鎮痛剤(例:ロキソニンやカロナールなど)を服用するのが効果的です。
- 市販の痛み止め(イブプロフェン、アセトアミノフェンなど)を使うことも可能ですが、歯科医の指示に従いましょう。
- 痛み止めの過剰摂取は肝臓に負担をかけるため、用法・用量を守って服用してください。
自然な痛みの軽減方法
- 冷やす:抜歯後24時間以内は、頬の外側からタオルに包んだ保冷剤や氷嚢で冷やすと、痛みを和らげることができます。1回20分を目安に、10分休憩を挟みながら冷却しましょう。
- 安静にする:体を動かしすぎると血流が良くなり、痛みが増すことがあります。術後24時間は安静にしましょう。
- 頭を高くして寝る:枕を高めにすると、血流が抑えられ腫れや痛みが軽減されます。
抜歯後の腫れの軽減方法
腫れのピークと持続期間
抜歯翌日から腫れが目立ち始め、2~3日目にピークを迎えます。その後は徐々にひいていき、通常は1週間以内に収まります。
冷却の仕方
- 抜歯直後から24時間は冷やすことで腫れを抑える効果があります。
- 氷嚢や冷却シートを頬に当て、20分冷やして10分休むサイクルを繰り返します。
- 24時間を過ぎたら、温めることで腫れを引かせる方法もあります(温湿布やぬるめのお風呂など)。
回復を早める方法
- 栄養バランスの良い食事を摂る(特にビタミンCやタンパク質を意識)。
- 十分な睡眠をとり、体の回復力を高める。
- 適度に水分を補給し、脱水を防ぐ。
抜歯後に避けるべき行動
強いうがいをしない
抜歯当日は、うがいを控えましょう。血の塊(血餅)が取れてしまうと、治癒が遅れる原因になります。
運動や長風呂を避ける
運動や熱いお風呂は血行を良くしすぎてしまい、出血や腫れの悪化を招くため控えましょう。
喫煙・飲酒をしない
- 喫煙すると血流が悪くなり、傷の治りが遅くなります。また、吸う動作で血餅が取れやすくなります。
- 飲酒は血行を促進し、出血が止まりにくくなるため、最低でも術後24時間は控えてください。
ストローを使わない
ストローを使うと口腔内に陰圧がかかり、血餅が剥がれてしまう可能性があります。抜歯後1週間程度は避けましょう。
傷口を舌や指で触らない
気になるかもしれませんが、傷口をいじると感染の原因になるため触らないようにしましょう。
抜歯の際によくある質問と回答
- Q抜歯後の痛みはどのくらい続きますか?
- A
通常、抜歯後の痛みは麻酔が切れた後から数日間続くことがありますが、鎮痛剤でコントロールできる場合がほとんどです。痛みがひどくなる場合や一週間以上続く場合は、歯科医に相談してください。
- Q抜歯後の出血が続いているのですが、どうしたら良いですか?
- A
抜歯後、軽度の出血は数時間続くことがありますが、ガーゼを患部に当ててしっかり噛むと止まりやすくなります。もし出血が長時間続く場合は、冷水でゆすぐ、またはアイスパックで冷やすと効果的です。数日経っても出血が止まらない場合は歯科医院に連絡してください。
- Q抜歯後の腫れや炎症はどのくらい続きますか?
- A
抜歯後の腫れや炎症は2~3日目に最も強く出て、1週間ほどで引くことが多いです。冷たいタオルやアイスパックで患部を冷やすと腫れが抑えられます。腫れがひどくなったり、化膿する場合は、歯科医に相談してください。
- Q抜歯後、食べてはいけないものはありますか?
- A
抜歯当日は、硬い食べ物や熱い食べ物、アルコール類は避け、スープやゼリーなど柔らかい食べ物をお勧めします。治癒が進むにつれ、通常の食事に戻せますが、しばらくは患部を避けるようにしてください。
- Qいつから通常の歯磨きを再開できますか?
- A
抜歯当日は患部を避けて、歯磨きを優しく行ってください。翌日以降は、軽くゆすいで汚れを落としてください。1週間ほど経過してから通常の口腔ケアを心がけるとよいです。
- Q抜歯後の運動やお風呂は控えた方がいいですか?
- A
抜歯直後の激しい運動や長時間の入浴、サウナは避けた方が良いです。血行が良くなることで出血が長引く可能性があるため、数日は安静を心がけましょう。
- Q抜歯した部分が何かの拍子に痛くなったり違和感を感じるのですが、問題ないでしょうか?
- A
抜歯後、しばらくは痛みや違和感が残ることがありますが、徐々に収まります。しかし、痛みが強くなったり、膿が出ているように感じる場合は、感染の可能性もあるため、歯科医に診てもらうことをお勧めします。