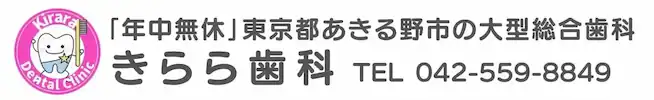矯正治療において「叢生(そうせい)=乱ぐい歯」と「すきっ歯(空隙歯列)」のどちらが難しいかという問いに対しては、症例によりますが、一般的には“すきっ歯”のほうが治療が難しいとされることがあります。
■ 叢生(乱ぐい歯)
- 歯がデコボコに並んでいる状態で、主に「顎が小さい」や「歯が大きい」ことが原因。
- 治療では、歯を整列させるためのスペースを確保する必要があり、抜歯や歯列拡大で計画的にスペースを作り出すことができます。
- ワイヤー矯正により、比較的コントロールしやすく、歯の位置を整えやすい傾向があります。
- 長期的な実績が多く、治療計画を立てやすいことも利点です。
■ すきっ歯(空隙歯列)
- 歯と歯の間にすき間が空いている状態で、「顎が大きい」「歯が小さい」「歯の欠損」などが原因。
- 一見すると簡単に見えますが、空いたスペースをきれいに閉じることは意外と難しく、歯が動いても後戻りしやすいという特徴があります。
- 前歯の正中離開(前歯のすき間)が目立つ場合、審美的に高い精度が求められることも多く、舌癖や上唇小帯の影響なども加味して治療を進める必要があります。
- 治療後にスペースが再び開かないよう、保定(リテーナー)管理もより慎重に行う必要があります。
【まとめ】
| 比較項目 | 叢生(乱ぐい歯) | すきっ歯 |
|---|---|---|
| 難易度 | やや低め | 高め |
| スペース処理 | 作る(拡大・抜歯) | 閉じる(後戻りしやすい) |
| 治療の安定性 | 高い | 後戻りしやすい |
| 対応矯正法 | 幅広く適応 | 方法に制限が出る場合も |
| 審美面の要求 | 一般的 | 高い傾向あり |
【結論】
叢生は「スペースを作る」治療で対応可能な一方、すきっ歯は「空いているスペースをきれいに閉じる」ことが求められ、後戻りのリスクや審美性への配慮が必要なため、治療が難しいとされることがあります。
精密な診断と適切な計画が、矯正治療成功の鍵となります。まずは専門医の相談を受けることをおすすめします。