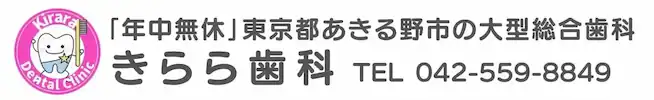スライディングメカニクスとは?
「レクトアンギュラーワイヤー(角ワイヤー、レクトワイヤーとも呼ばれます)」と呼ばれる断面が四角形のワイヤーを使用する矯正方法です。
スライディングメカニクスでは、早期にレクトアンギュラーワイヤーを装着し、ワイヤーを後方へ滑らせながら6前歯を一緒に後退させることができる。
一方、スタンダードエッジワイズ方ではワイヤーをスロットやチューブの中を滑らせるのではなく、クロージングループによって摩擦抵抗を受けずに抜歯空隙を閉鎖するのが特徴である。
スライディングメカニクスでは、018 X 025スロットでも022 X 028スロットでも行うことができる。
022 X 028スロットの方がバインディングなどの弊害は少ない。
🔧 スライディングメカニクスを阻害する主な要因
1. 摩擦抵抗(Friction)
🔹ブラケットとワイヤー間の摩擦
- 特にステンレスワイヤーとメタルブラケット以外の組み合わせでは摩擦が大きくなりやすい(例:セラミックブラケットは摩擦が高い)。
- リガチャーワイヤーの締め方が強すぎると、摩擦が増大します。
🔹結紮方法の影響
- メタルリガチャーは結紮が強くなりやすく、摩擦が増加。
- エラスティックモジュールも時間とともに劣化し、予測しづらい摩擦が生じます。
2. ブラケットの精度
- ブラケットスロットとワイヤーの**遊び(クリアランス)**が小さすぎると、スムーズな移動ができない。
- スロットが汚れていたり、バリ(成形の不良)がある場合も動きを妨げます。
3. ワイヤーの変形や劣化
- 使用中のワイヤーが曲がっている・傷がある・酸化して滑りが悪いなどの場合、動きが阻害されます。
- 特に矩形ワイヤーでのコントロール時に起こりやすいです。
4. アンカレッジの問題
- 抜歯スペースを閉じる際に、アンカレッジ(固定源)が不安定だと、後方臼歯が動いてしまい、前歯が予定通りに移動しにくくなります。
- 特にミニスクリュー(TAD)を使わずにリトラクションを行う場合、Anchorage Lossが問題になります。
5. 歯の生物学的反応(Bio-response)
- 歯周組織の状態(例:炎症、歯槽骨の硬さ)によっても歯の動きやすさが変わります。
- 加齢や代謝低下、喫煙などの要因でも歯の移動速度が落ちる可能性があります。
6. アーチワイヤーのたわみや撓み
- 長いスパンのワイヤーでは、移動時に**たわみ(deflection)**が生じ、力がロスして動きが悪くなることがあります。
💡まとめ表
| 阻害要因 | 説明 |
|---|---|
| 摩擦抵抗 | ブラケット・ワイヤー間の摩擦が高すぎる |
| 結紮の強さ | 強すぎるとワイヤーが動かない |
| ブラケットの精度 | スロットが不正確・汚れがある |
| ワイヤーの劣化 | 傷・曲がり・酸化による滑りの悪化 |
| アンカレッジの弱さ | 臼歯が動いて前歯が引けない |
| 歯周の状態 | 骨密度、炎症、代謝の影響 |
| ワイヤーの撓み | 長いスパンで力が逃げる |
🔷 クリンパブルフックの設置位置の比較
| 位置 | 使用目的 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 3番と4番の間 | 抜歯後の空隙閉鎖(前歯のリトラクション) アンカレッジとの牽引(TADなど) | ・犬歯の後方移動を含めたコントロールがしやすい ・動かす歯の中心(CR)に近く、力の方向が安定 | ・やや遠心寄りで、前歯単独の牽引にはやや不利になることも |
| 2番と3番の間 | 前歯6本の一括リトラクション時 特に前歯群をまとめて後方移動させたい場合 | ・前歯のトルクコントロールがしやすい ・唇側へのフレアを抑えやすい | ・犬歯が残っている場合、犬歯の動きと干渉することがある ・スペースの確保がやや難しいことも |
✅ 臨床的なおすすめ(用途別)
▶ 抜歯症例で前歯群を一括リトラクション →
→ 2番と3番の間にフックを設置
(トルクを効かせながら前歯6本をしっかり引ける)
▶ 抜歯症例で犬歯も含めたリトラクション →
→ 3番と4番の間にフックを設置
(犬歯と前歯の移動を一体として制御可能)
💡補足:ミニスクリュー(TAD)併用時
TADからの力のベクトルが理想的にかかる位置としては、3番・4番間の方がより安定した遠心移動の軌道を得られることが多いです。
📝まとめ:
- 前歯のトルク重視・前歯のみを一括で引くなら「2番-3番」
- 犬歯も含めた全体の前方ユニットのコントロールなら「3番-4番」