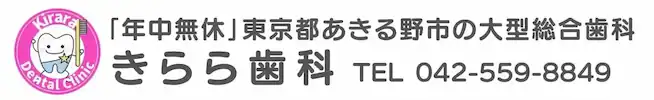歯科治療で局所麻酔(注射麻酔など)を受けた後は、麻酔が完全に切れるまでの間に以下のような点に注意が必要です。痛みや出血の予防だけでなく、麻痺による思わぬケガを防ぐ目的があります。
きらら歯科で使用している麻酔薬について
当院で使用している麻酔薬は以下の四種類です。患者様の既往歴・歯の状態に応じて使い分けを行なっております。
- キシロカインカートリッジ
- エピリドカートリッジ
- オーラ注カートリッジ
- スキャンドネストカートリッジ
キシロカインカートリッジ

キシロカインカートリッジは、歯科治療において痛みを軽減するために広く使用されている安全性の高い局所麻酔薬です。
エピリドカートリッジ

エピリドカートリッジとキシロカインカートリッジは、どちらもよく似た効果を持つ局所麻酔薬ですが、配合されている成分の割合が少し異なります。そのため、麻酔効果の持続時間や、患者さんへの作用の強さなどがわずかに異なる場合があります。
オーラ注カートリッジ

オーラ注カートリッジは、歯科治療において痛みを軽減するために広く使用されている安全性の高い局所麻酔薬です。キシロカインカートリッジと同様の効果が期待できますが、配合成分の割合がわずかに異なるため、歯科医師は患者さんの状態に合わせて適切な麻酔薬を選択します。
スキャンドネストカートリッジ

スキャンドネストカートリッジの特徴
- 主な成分: メピバカイン塩酸塩という成分が主成分です。
- 効果: 神経の働きを一時的に麻痺させることで、痛みを感じなくさせます。
- 用途: 歯科治療における浸潤麻酔や伝達麻酔など、様々な治療に使用されます。
- メリット:
- 治療後のしびれが短い: メピバカインは、他の麻酔薬と比べて治療後のしびれが短いという特徴があります。そのため、短時間の処置に適しています。
- 血管収縮薬不使用: スキャンドネストは、血管を収縮させる薬剤(血管収縮薬)を含んでいません。そのため、血管収縮薬にアレルギーのある方や、循環器疾患のある方でも使用できる可能性があります。
- 防腐剤不使用: パラベンなどの防腐剤も含まれていません。そのため、防腐剤アレルギーのある方でも使用できる可能性があります。
麻酔でのアレルギーについて
現在、きらら歯科で使用している麻酔薬は安全性が非常に高く、アレルギー反応を起こすようなことはほとんどありません。

麻酔をした後に、気分が悪くなったりすることがありますが、これは局所麻酔薬のアレルギーではなく、緊張感や恐怖感などの精神的な影響によって生じる場合が多いです。
噛む・やけどに注意
麻酔をした後は唇・頬がしびれて感覚がなくなっています。
唇や頬を噛んだりしないように気を付けて下さい。また、熱い物を口にしても感覚が無い為やけどの恐れがあります。
お子様の麻酔の場合

特にお子様は気になってお口の中を触ったり噛んでしまうことがあります。頬っぺたや唇が、噛んで遊んでいると腫れあがってしまうことあります。

そのため親御様がくれぐれもご注意して下さい。
麻酔の効いている時間
キシロカイン・エピリド・オーラ注を使用した場合

歯医者で、虫歯の治療などで行なった麻酔ではしびれている感覚が2~6時間は続きます。
麻酔が効いている時間には個人差がありますが、麻酔の後2~6時間くらいはしびれが残ることがあります。感覚が戻るまでは食事を避けて下さい。
スキャンドネストを使用した場合
きらら歯科では、麻酔が早く切れるスキャンドネストという局所麻酔薬もあります。
麻酔剤の効果を保つ目的で添加されるアドレナリンなどの血管収縮剤が添加されていないのが特徴で、血圧や心拍数を上昇させる作用がないことから、高血圧症、糖尿病、動脈硬化症、甲状腺機能亢進症の患者や小児の治療に向くとされる。

この麻酔薬には、血管収縮薬が含まれていません。そのため、20~30分ほどで麻酔の効果がきれます。麻酔の効果がきれた後は、食事を再開しても大丈夫です。
その他のアフターケア
- 口腔内の清潔保持
- 食事後はできる範囲で歯磨きやうがいをし、清潔を保ちましょう。
- 強くうがいをすると血餅(出血部位のかさぶた)が取れる可能性があるため、特に抜歯後は優しくゆすぐ程度にしてください。
- 強い運動や飲酒を避ける
- 激しい運動や飲酒は血行を高め、出血や痛みを強めることがあります。医師からの指示がある場合はそれに従い、安静を心がけてください。
- 違和感や異常があればすぐ相談
- 麻酔後の腫れや痛みがひどい、しびれや感覚麻痺が長時間続くなど、普段とは違う症状を感じた場合は遠慮なく歯科医院に問い合わせましょう。
まとめ
- 麻酔が残っている間は、口の感覚が麻痺していることを前提に行動しましょう。
- 唇や頬を噛まない、熱いものを口にしないなどの基本的な注意を守ることで、麻酔後に生じるトラブルを防ぐことができます。
- 麻酔後の痛みや腫れ、出血が続く・悪化する場合は、早めに歯科医院に連絡して指示を仰いでください。